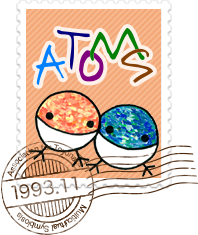第68回 選択的夫婦別姓を先行く国際結婚
吉嶋かおり(よしじまかおり)
この原稿を書いている今年、夫婦別性制度の導入へ向けた民法改正法案が国会に提出されました。1996年の法制審議会による答申から既に30年近くたっていますが、改正法案の成立は不透明というニュースが流れてきました。この「おしらせ」が発行される頃はどうなっているでしょうか。
夫婦別姓導入への反対意見として、家族の姓が異なっていると家族の一体感が損なわれるとか、子どもへ悪影響を及ぼすという考えがあります。しかし、国際結婚の場合、婚姻時は原則、夫婦別姓なのです。このことをどのくらいの人が知っているでしょうか?
これは、戸籍法によって起きている状況です。
日本国籍の人同士が結婚するときは、戸籍は一つの姓のみなので、夫婦のどちらかの姓を選択しなければなりません。しかし戸籍は日本国籍の人のみに適用されるため、外国籍の人と結婚する時は、外国籍の配偶者は戸籍に記載されないのです(婚姻の事実は記載されますが、戸籍の構成員として登録されません)。つまり、日本国籍の人は、結婚前の姓のままで、結婚により新たな戸籍を作成するという流れになり、一方で外国籍の人も、その人の名前はそのまま維持されるので、原則として夫婦別姓になるのです(ですので結婚を意味するようになった「入籍する」という表現は国際結婚では当てはまりません)。日本国籍の人は、手続きをすれば、外国籍配偶者の姓や複合名に変更することもできます。ですので、国際結婚は「選択的」夫婦別姓制度と言えます。
この夫婦に子どもが生まれた場合(子どもを養子にした場合も)、子どもが日本国籍であれば、日本国籍の親の戸籍に登録されますが、外国籍だけの場合は、親の戸籍には登録されません。戸籍は日本国籍の人だけを対象としているので、このように、外国籍の配偶者だけでなく、日本国籍を持っていない子どもも同様に戸籍がなく、戸籍上は一つの「家族」としては構成されないのです。
でも、家族は家族。
センターに来ている人々には、一つの姓の家族も、別姓の家族もいます。親と姓が異なる子もいます。子どもの名前も多様です。
そういういろいろな国の、さまざまな家族が示してくれているのは、「家族の一体感」や家族関係のかたちは、「姓」とは関係がないということです。
国際結婚は、毎年、全婚姻の約3.5%を占めており、その人たちはすでに家族の姓を選択している状況にいます。日本国籍の人だけによって構成される家族を前提とした戸籍制度を越えて、家族はすでに多様なかたちで社会で暮らしているのです。
吉嶋かおり(よしじまかおり)
外国人のための多言語相談サービス相談員。臨床心理士。2006年から担当しています。
どんな相談があるの?相談って何してるの?という声にお応えできるよう、わかりやすくお伝えできればと思ってコラムを書いています。