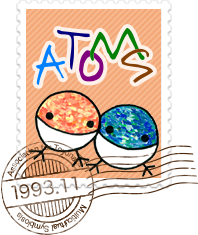2024年12月 少しだけ北の国から@福島(第34回)
辻明典(つじあきのり)
『後から後から』
「なんか、生かされてんな」
「誰に?」
「それが、わからんのですわ」
今年公開された、映画「生きて、生きて、生きろ」(監督:島田陽磨)のなかに出てくる言葉です。震災と原発事故から13年。福島では、時間を経てから発症する遅発性PTSDなど、こころの病が多発。若者の自殺率や児童虐待も増加。そのような状況のなかで奔走する医療従事者の姿を捉えたドキュメンタリーです。
拙稿よりも、よりリアリティをもって福島の現実が描かれているので、おすすめの作品です。
私も、福島の、特に浜通りで暮らしていると、曰く言い難いのですが、なんとはなしに感じられる雰囲気があります。例えるなら、「待てない」「聴けない」「落ち着きがない」「他者との距離感がつかみがたい」といった人が増えたような、浮き足だった空気感のようなものです。(もちろんこれらが、全ての人たちに当てはまるような特徴ではない、ということは申し添えておきます。)
ただ、原発事故が起きたときに生まれた子どもは、中学生になりました。事故前後に出生した子どもたちの保護者は、当時は恐らく被災しており、避難を強いられ、土地を転々と移動せざるを得ない状況に強制的に置かれた人たちも多かったはずです。
幼子が不安を感じたとき、そばにいる大人が優しく声をかけ、そのケアを担うことはよくあることでしょう。しかし、原発事故によって長期にわたって翻弄された状態にあれば、大人も余裕を失い、それが十分にできない状況が生まれやすいことは、容易に想像できるでしょう。大人が余裕を失えば、そのしわ寄せは、弱い立場にある子どもにいってしまいます。それは、父親や母親をはじめとする家族が責めを受けるべき、ということではありません。これは間違いなく親と子どもを翻弄した国家の責任なのです。
「何を今更…」「それは、福島だけの問題ではない…」という声も聞こえてくる気もします。しかし、先ほどご紹介した映画「生きて、生きて、生きろ」のなかで「遅発性PTSD」が描かれているように、後発的に問題が吹き出してくるのではないか、という気がしてなりません。考えすぎでしょうか?それなら、それでいいのですが。
辻明典(つじあきのり)
協会事業(哲学カフェ、プロジェクト“さんかふぇ”等)に参加していた辻明典さんが、2013年度より故郷である福島県南相馬市に戻り、教員をしています。辻さんからの福島からの便りをどうぞ。