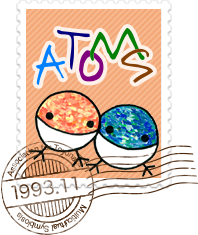2025年3月 이모저모通信(第20回)
皇甫康子(ふぁんぼかんじゃ)
短大に入学したとき、大学の先輩から大阪市内の中学校で朝鮮文化研究会の指導をしないかと誘われた。「外国人登録証」の授業をするので、準備の学習会をすることになり、先輩に紹介されたのが、東大法共闘編の「告発・入管体制」(1971年)だった。日本の侵略戦争、植民地支配の結果、戦後もたくさんの在日朝鮮人が日本に残留したが、その処遇はひどいものだった。
そうか、日本の最高峰の知識を集め考えられたのが「入管法」で、いつ強制送還されるか分からない不安定な状況に私たちを追いやっていたのか。外国人登録証の14歳からの常時携帯や、紛失、更新遅延の時にはまるで犯罪者扱い。息の詰まる日常の中で、「国籍条項」の壁がたちはだかり、健康保険に入れなかったり、進学や就職から排除されたりと、さんざんな思いをさせられてきた。もう我慢できないと声を上げた「在日」の先輩や仲間、後輩たちのお陰でかなりの改正を勝ち取ったが、常に道を阻まれ「在日特権」を訴え、「在日」を痛めつける集団まで現れた。制度が変わり、外国人登録証から在留カードへと変わっても、強制退去強制はそのまま残っており、相変わらずの差別や排除を受け、基本的人権ですら脅かされる私たちにどんな特権があるのか。植民地支配の補償のないまま、自力で生きてきた「在日」に対して、「何も権利を付与しないで死んでいくのを待つ」「差別をして劣等感を持たせ日本に同化させる」などの政府の政策は効を奏し、多くの「在日」が通称名(日本名)で生活し、国籍を保持している「在日」も少数になっている。
たくさんのことを諦めることで生きてきた「在日」にとって、指紋押捺拒否運動とはどんな運動だったのか、『指紋押捺拒否・反外登法の闘いとはなんだったのか 40年後のいま、運動を振り返る』シンポジュームが11月30日、同志社大学で開催され、参加することができた。
反対するだけでは変革は無理なので、法を破っての抵抗運動を考えたという勇気。自治体の職員に告発しないよう働きかけ、味方につけるという作戦で、国に反旗を翻し、外国籍住民を守る職員に変容させていく熱意。関西では、「外登証世界の旅」で、外国人登録証を展示し、その非道さを訴えるというユニークな活動もあった。
激しい闘いの末、指紋押捺制度は2000年4月1日に廃止された。知恵を絞り、政府に立ち向かった当事者たちの勝利だった。シンポジュームの最後に、「『在日』は炭鉱のカナリアだ。日本社会がどのような社会なのか、「在日」への処遇をみれば理解できる」という訴えに共感し、他の外国籍住民と共に、資格ではなく永住する権利を獲得しなければと気持ちを新たにした。
「在日」の闘いの歴史を振り返るたびに、難民や移住者への処遇など、現在に通じる問題を考える糸口になる。連続する勇気ある行動が、私たちに生きる力を与えてくれるのだ。
皇甫康子(ふぁんぼかんじゃ)
2018年2月号に最終回を迎えた連載「なんじゃ・カンジャ・言わせてもらえば」の執筆者、皇甫康子さんの新しいコラムがスタートします。皇甫さんの想いとメッセージがイモヂョモ(あれこれ)詰まったコラムをどうぞ。